今年の門下生発表会は
10月に行われます。
いつも何を弾こうか散々迷うのですが
今回はすんなり
ドビュッシー『喜びの島』に決まりました。
ピアノ科の同級生がかっこよく弾いていたのが印象深く
最近、フォーレを弾く機会もあったり
少しフランスものの経験も増えてきたので
どちらかと言うと、苦手なフランスものですが
失敗してもいいからチャレンジしてみたい!
と思ってしまいました。
今回もまずは
曲の背景を知ることから始めたいと思います。
クロード・アシル・ドビュッシーについて
1862年8月22日 フランスのサン・ジェルマン・アン・レイで生まれる
父は陶器商を営んでいたが、裕福ではなかった。
1867年 パリに住み始める
1871年 パリ=コミューンで国民軍に加わっていた父が逮捕される。
その頃から父親の知り合いのモーテ夫人から音楽を学びはじめる。
1872年 パリ音楽院に入学
1880年 伴奏科で1等賞を得る・この年から3年間、ロシアはじめ各国に楽師をつとめる
1884年 ローマに留学中、ローマ大賞を獲得。文学に関心が深かったドビュッシーは
ヴェルレーヌやマラルメの詩にもとづく歌曲を作曲
1893年 『弦楽四重奏曲』『牧神の午後への前奏曲』で成功をおさめ
新進作曲家として認められたが、まだまだ生活は苦しく
ボヘミアン生活を強いられた
1901年 ようやく一流作曲家の仲間入り ドビュッシー40歳の時
1904年 弟子の母エンマと恋愛関係に
絶望した妻は拳銃自殺未遂 ボヘミアン時代の友人も去っていった
1905年 一粒種のシュシュことクロード=エンマ誕生
1914年 第一次世界大戦勃発 ドビュッシーは衝撃で創作力を無くす
1915年 直腸がんの手術を受ける
1917年 7月に療養地のサン=ジャン=ド=リューズでの公演が最後の演奏となった
1918年 3月25日死去 現在はパッシー(フランスの高級住宅街)の墓地に眠っている
喜びの島について
1904年に作曲
現在もルーブル美術館に所蔵されている
ジャン=アントワース・ヴァトーの
『シテール島の巡礼』に影響を受けて作曲された。
協会旋法である『リディア旋法』を使った曲である。
冒頭は長いトリルで始まり
カデンツァ(即興的に自由に演奏する部分)のように
演奏するので個性がでるところ
(いろいろなピアニストを弾き比べると面白い)
美しい島で喜びに満ち溢れて
天真爛漫にはしゃいでいる様子が
スキップしているようなリズムで表現されている。
最後のクライマックスには
冒頭と同じメロディーが繰り返され
華やかなトレモロで一気に盛り上がり
6音の下行する装飾音符を素早く弾き
最低音の『ラ』で完結する。


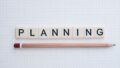
コメント